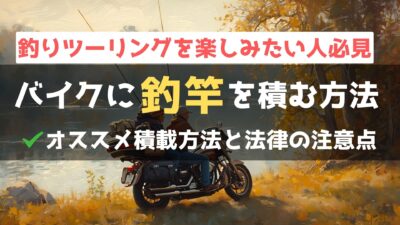
バイクで釣り竿を運びたい!違反にならない積載方法は?注意点も解説

当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

愛犬とバイクで出かけられたらな…
バイクに乗るだけでも楽しいですが、愛犬と風を切れたら、さらに嬉しいですよね。
問題は「犬をどうやってバイクに乗せるか」という点ではないでしょうか。
車に比べて小さく、シートの面積が少ないバイクに、そのまま愛犬を乗せるのは難しいです。

じゃあ、どうやって乗せたらいいの?
という方に向けて、この記事では、愛犬とバイクライフを楽しむための方法や必須グッズを解説していきます。
バイクに乗る上で重要な「法律」についても徹底解剖。
この記事を読めば、愛犬と安心・安全にバイクに乗る方法が全てわかっちゃいます!
【バイクのサイズ】×【愛犬のサイズ】でまとめたから、オススメグッズだけ知りたい人は、ここを参考にすればOKだよ
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | |
| スクーター | サイドカーなど の特殊装備 |
||
| 中型・大型バイク | |||
| 原付 |

愛犬とバイクでタンデムする前に、法律規制や違反事項について理解しておきましょう。
知らずに走行してしまうと、道路交通法に違反してしまうばかりか、自身や愛犬に危険が及んでしまう可能性があります。
道路交通法における犬の位置づけや、違反にならないためのポイントについて詳しく解説しますので、参考にしてください。
道路交通法では、犬は「積載物」として扱われます。
そのため、犬をバイクに乗せる際には、積載物としての規制を守る必要があります。
道路交通法第55条では、バイクに積載できる物の範囲と方法が定められています。
具体的には、積載物の横幅、高さ、長さ、重量に制限があります。
制限は、次の通りだよ
|
項目 |
規制範囲 |
|
横幅 |
バイク左右各30cm以内 |
|
高さ |
地面から2m以内 |
|
長さ |
バイクの前後各15㎝以内 |
|
重量 |
自動二輪車:60kg |
例えば、小型犬をキャリーバッグに入れてバイクに乗せる場合、そのキャリーバッグがバイクの横幅から30cmを超えないようにする必要があります。
さらに、地面から2mを超える高さに配置しないこと、バイクの後方に15cm以上出ないようにする必要があるのです。
このサイズに収まるグッズについては後述していますので、参考にしてみてくださいね。

愛犬をバイクに乗せる際、違反にならないためには次のポイントを守ることが重要です。
交通違反は、積載物の超過だけではありません。
犬が飛び出して周囲を危険にさらした場合にも違反となります。
具体的な違反事例についてみてみましょう。
違反で済めば良いですが、事故になると損害賠償なども発生し、あなたに大きな責任がのしかかります。
愛犬の命にも危険があるため、安全を最優先に考え、適切な装備と方法を選ばなければなりません。

積載グッズのことはよく分からない…
という方もご安心ください。
次からはグッズの種類やおすすめを紹介します。
もし迷った時は、おすすめグッズの中から、あなたが気に入ったものを選べば間違いないでしょう。
まず、愛犬とバイクに乗るためのグッズの種類から解説していきます。

愛犬とバイクに乗るためのグッズは、主に3種類あります。
愛犬とのバイクツーリングを楽しむためには、安全性と快適性を兼ね備えたグッズが欠かせません。
適当なものを選んでしまうと、愛犬や周囲の方を危険な目に合わせてしまいます。
せっかくツーリングするなら、安全に行いたいですよね。
そんな快適なツーリングを実現する、グッズの種類について解説します。

リュック型キャリーバックは、小型犬をバイクに乗せる方にピッタリのグッズです。
リュック型キャリーバックは、飼い主の背中あるいは胸の位置で愛犬を固定できるため、バイクの操作性を損なうことがありません。
そのため、安全に愛犬とのツーリングを楽しむことができます。
また、愛犬も安定した位置にいるため、安心感を持てるでしょう。
リュック型キャリーバックは、耐久性のある素材で作られており、通気性の良いメッシュ素材を採用していますので、ワンちゃんも快適に過ごすことができます。
内部にはリードを固定できるフックが付いているので、飛び出す心配もありません。
ただし、常に背負っている状態になるため、肩に負担がかかり長距離では疲れやすくなります。
長距離を移動する場合は、休憩をこまめに取るようにしましょう。

小型犬で短距離の場合に最適だね

ゲージタイプのキャリーは、中型犬や長距離の移動に適したグッズです。
ゲージタイプのキャリーは、非常に頑丈なため、急ブレーキや転倒時にも愛犬をしっかり保護してくれます。
固定用のストラップを正しく使用すれば、バイクにしっかり取り付けることができ、走行中にゲージが落下することはありません。
キャリーゲージは、耐衝撃性のプラスチック製で作られていることが多いです。
通気口も多く設けられているので、走行中でも愛犬が快適に過ごすことができます。
ゲージタイプは大きく、安定感があるため、中型犬を飼っている方やロングツーリングを行う方におすすめです。

中型犬や長距離にも対応できる万能タイプだね

抱っこ紐(スリング)タイプは、特に小型犬やバイクに慣れていないワンちゃんに最適です。
飼い主の前に抱え込む形で固定するため、ワンちゃんが安心感を持ちやすいという特徴があります。
飼い主との密着度が高く、ワンちゃんが落ち着いていられるので、バイクに慣れさせるのにも役立つでしょう。
抱っこ紐は、柔らかい素材が使用されており、犬の体にフィットするようデザインされています。
ストラップで長さ調整できるので、飼い主の体形に合わせてしっかりホールド可能です。
内側にリードを固定するフックが付いているものであれば、あなたやワンちゃんの安全性を確保することができます。
抱っこ紐(スリング)タイプは、飼い主との距離が近い分、ワンちゃんにとっても安心感が高いグッズです。
初めてバイクに乗るワンちゃんに特に有効なので、ぜひ試してみてください。

小型犬やまだバイクに慣れていない子に最適だよ
| 愛犬をバイクに乗せるためのグッズの特徴比較 | |||||
|
グッズタイプ |
適用犬種 |
利便性 |
安全性 |
快適性 |
価格帯 |
|
リュック型キャリーバッグ |
小型犬 |
高い |
高い |
中~高 |
3,000~10,000 |
|
ゲージ |
中型犬 |
中 |
非常に高い |
高 |
20,000~ |
|
抱っこ紐(スリング) |
小型犬 |
高い |
中~高 |
高 |
2,000~8,000 |
これらのグッズを活用することで、安全で快適なバイクライフを楽しむことができます。
それぞれの特徴をしっかり理解し、愛犬に最適なグッズを選びましょう。

もうちょっと具体的に選び方を知りたい!
という方のために、次は愛犬をバイクに乗せるグッズの選び方について解説します。

愛犬とバイクでツーリングを楽しむには、適切なグッズ選びが重要になります。
バイクや愛犬に合わないグッズを選ぶと、思わぬトラブルが起きる可能性もあります。
安全に走行するために抑えるべきポイントは、次の3点です。
正しいグッズを選んで、快適なバイクライフを実現していきましょう。
バイクの種類に応じて、適切なグッズを選ぶことが、安全かつ快適なバイクライフの第一歩になります。
バイクの種類によって、設置できるキャリーバッグやゲージのサイズ、形状、取り付け方法が異なります。
特に、スクーターや中型・大型バイク・原付などでは積載スペースや固定方法が異なるため、それに合わせたグッズが必要です。
バイクの種類に応じたグッズを選べば、安心・安全にツーリングしやすくなります。
愛犬の安全性と快適性を守るには、愛犬の種類・サイズに合ったグッズを選ぶ必要があります。
小型犬にはキャリーバックや抱っこ紐が適していますが、中型犬以上の場合はゲージが必須です。
大きな犬を抱っこしながら運転するのは至難の技であり、飼い主・愛犬どちらにも負担がかかってしまいます。
愛犬の種類やサイズに合ったグッズを選べば、飼い主も愛犬も安心してツーリングに行けます。
バイクは不安定な乗り物であるため、安全性の高いグッズを選ぶことが非常に重要です。
安全性の高いグッズを選ぶことで、事故やケガのリスクを最小限に抑えることができます。
具体的には、しっかりと固定できるものや、耐衝撃性の高い素材で作られたものを選ぶことで、万が一の事故でも愛犬を守ることができます。
安全性の高いグッズを選ぶことで、愛犬を事故やケガから守ることができます。
固定用ストラップや耐衝撃性素材、通気性の良い設計など、安全性を重視したグッズ選びを心がけましょう。

では、いよいよ愛犬とバイクに乗るためのオススメグッズを解説します。
先に紹介した、3つの種類に分けて紹介します!
迷った時は、この中から選べば間違いありません。
では、まずリュック型のキャリーバックから解説します。

リュック型は、小型犬で短距離走行に向いているんだったね

オシャレなリュックで愛犬とのツーリングを楽しみたい方は、シティドッグのキャリーバッグリュックがおすすめです。
こちらの魅力は次の通り。
せっかくお出かけするのであれば、飼い主さんもワンちゃんもオシャレしていきたいですよね。
このバックでは、その願い、叶います!
さらに、オシャレだけじゃない安心・安全の構造なので、見た目と機能性を両立させたキャリーバックと言えます。
愛犬が入ったこのリュックを背負って、颯爽とバイクで通り過ぎれば、道端の方が振り返ること間違いなしです。

使いやすさにこだわりたい方は、WinSun ペットキャリーバッグがおすすめです。
このバックの魅力は次の通り。
WinSun ペットキャリーバッグの最大荷重は7㎏。
幅広の肩ベルトがあるので長時間背負って走行しても疲れにくいです。
また、多くのペットリュックは大きく、かさばりやすいですが、WinSun ペットキャリーバッグなら、そんな心配はいりません。
使わない時はたたんで片づけておくことも可能です。
カラーはブラックとベージュの2種類から選べます。
シンプルな見た目で、使いやすさを重視したい方におすすめの一品です。

汎用性の高いリュック型キャリーをお探しの方は、Wildgogoのペットキャリーがおすすめです。
こちらの魅力は次の通り。
Wildgogoのペットキャリーは機能性に富んでおり、ツーリング中の「これがあったらな」を叶えた一品です。
1番の魅力は2倍まで拡がる拡張機能。
出先で外に出すことはできないけれど、くつろいでもらいたい。
そんな時に拡げることで、愛犬と一緒にゆったり過ごすことが出来ます。
多機能なバックを求めている方におすすめです。
次にバイク用ペットゲージについて解説します。
ゲージも様々な種類がありますが、ここではバイク専用のものを解説します。
理由は、専用のものでないと安全性が保障できないからです。
ちなみに、バイク専用のゲージは少なめ。
そのため、ここでは信頼性の高いものを1つに絞ってピックアップしました。
リアキャリアに積めば、飼い主も愛犬も負担少なくツーリングを楽しむことができます。

ゲージは中型犬にも長距離にも対応できる万能型!

PSLERのオートバイ用ペットクレートは、カゴ感のないオシャレなゲージを求めている方におすすめです。
次のような特徴があります。
様々な機能を持っているのはもちろん、多くのゲージによくある「ペットのゲージっぽさ」がないカジュアルなゲージです。
プラスチック製のゲージだと「ワンちゃんが運ばれている」状態になります。
元々はハーレーに使われていたゲージで、見た目にもこだわった一品。
このゲージを使えば、道行く人に「ワンちゃんが一緒にツーリングしている」と囁かれるでしょう。
抱っこ紐の利用は小型犬に限られますが、使い勝手がよく、密着して安心感を高められるため、初めてバイクに乗るワンちゃんにもおすすめです。
ただし、適切なものを選ばないと、愛犬が走行中に飛び出してしまう恐れもあります。
ここでは、数ある抱っこ紐の中から、おすすめのものを3つ紹介します。

抱っこ紐は、小型犬やバイクに慣れていない子にオススメだよ

安全性と快適性を重視したいなら、CHMKSTCのペットスリングがおすすめです。
理由は次の通り。
2重でペットの飛び出しを防止してくれるので、中で暴れてしまっても飛び出すようなことがありません。
ただし、抱っこ紐なので、落ち着きのなさすぎるワンちゃんには不向きです。
また、生地はコットンを使用しているので、ワンちゃんにとっても最高の肌触り。
歩いている間に寝てしまったというレビューも多数見受けられました。
抱っこ紐選びで迷っている方は、まずはこの商品で慣れていくと良いでしょう。

こだわりの色で愛犬と出かけたい方は、CREAS WINGのペットスリング一択です。
魅力は次の通り。
12色ものラインナップがあり、こだわりのカラーで愛犬とのツーリングを楽しめます。
見た目だけでなく、ペット専門学校の講師監修で安全性・快適性もばっちり保証!
こだわりの抱っこ紐で優雅にツーリングを楽しめること間違いなしです。

使うなら国産のものを選びたい!という方は、ReFUNAのペットスリングがおすすめです。
次のような特徴を持っています。
海外製の商品も、もちろん信頼性の高いものばかりですが「国産」と聞くと、より一層安心感が増しますよね。
それだけでなく、名のある講師が監修しており、ペット専門の雑誌にも載るほど評価が高い抱っこ紐です。
見た目もカジュアルで、カラーも5色から選べるので、お出かけの際にも一目惹く商品。
国産の信頼性と安心感が欲しい方は是非お試しください。

愛犬とのタンデムツーリングは非常に楽しいですが、安全に楽しむためには準備と練習が不可欠です。
練習もせずにいきなりツーリングしてしまうと、思わぬ事故を招いてしまう可能性もあります。
愛犬にいきなり怖い思いをさせては、一緒にツーリングを楽しむのは難しくなってしまうでしょう。
そこでこの章では、愛犬と安全にタンデムするためのポイントを2つ解説します。
これらのポイントを押さえ、愛犬とのツーリングを安全かつ快適に楽しみましょう。
愛犬とバイクでタンデムをする際は、短い距離からゆっくり始めましょう。
バイクは犬にとって未知の体験であり、慣れるまでに時間がかかるため、短い距離から少しずつ慣れさせる必要があります。
また、飼い主自身も愛犬とバイクに乗る感覚を掴むために、まずは短い距離で練習する必要があるのです。
ワンちゃんが落ち着いて乗れるようになれば、安全にツーリングできます。
最初は自宅周辺や近所の公園までの短距離を走ります。
徐々に距離を伸ばしていくことで、愛犬はバイクの振動や音に慣れることができます。
バイクの振動や騒音は、ワンちゃんに大きな不安やストレスを与えます。
必ず短い距離から始め、慣れさせていきましょう。
落ち着いた様子で乗れるようになれば、長距離ツーリングも夢ではありません。
愛犬とのタンデムツーリングは、段階的に練習を重ねることが重要です。
1回目で落ち着いていたからといって、いきなり長距離ツーリングに行くことはおすすめできません。
急な変化は愛犬のストレスとなり、パニックを引き起こしてしまう可能性があるからです。
回数を重ねて、慣れさせることが重要です。
愛犬をバイクに乗せる時は、以下のステップを参考に、段階的な練習を進めてください。
|
ステップ |
詳細 |
|
初回の練習 |
自宅の庭や駐車場で静止した状態のバイクに犬を乗せる |
|
短距離の走行 |
自宅周辺や近所の公園までの短距離を走行 |
|
中距離の走行 |
数キロメートルの中距離を試し、休憩を挟みながら進める |
|
長距離のツーリング |
最終的に長時間の走行に慣れさせる |
愛犬との安全で楽しいタンデムツーリングを実現するためには、焦らず、慎重に練習を重ねることが大切です。
乗せる際に吠えたり怯えたりした場合は、すぐに練習を中止してください。
愛犬に心理的なストレスを与えてしまいます。
タンデムの練習をする際は、常に反応を観察し、短い距離でも乗れたことを褒めてあげましょう。
ワンちゃんに「バイクは楽しい」と思ってもらえれば、いつでもどこでも、愛犬とタンデムツーリングすることができます。
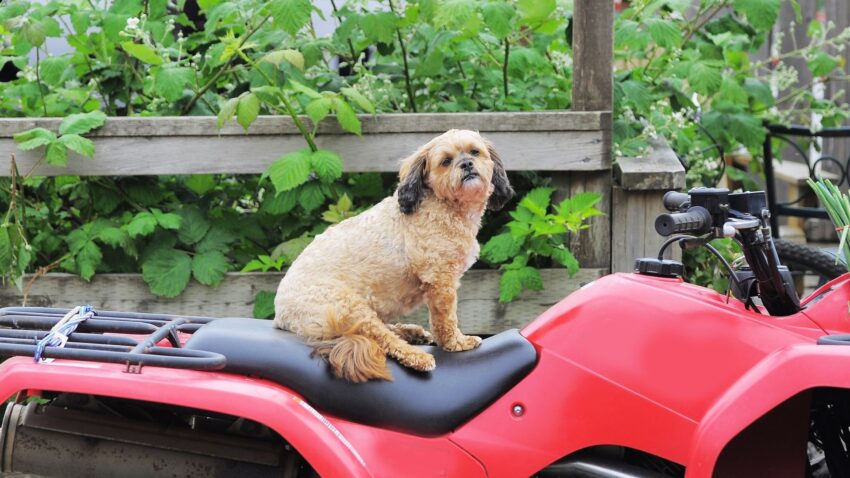
グッズを揃え、コツコツと練習を行えば、愛犬とバイクツーリングできる日はすぐそこです。
ただし、ツーリングする際にはいくつか注意点があります。
いくら交通ルールを守り、信頼性が高いグッズを使用しても、愛犬が安心して楽しめないようでは、飼い主の自己満足になってしまうのです。
最後に、愛犬とのツーリングを楽しむための注意点を3つ解説します。
この点を押さえ、ワンちゃんと最高のバイクライフを楽しんでいきましょう。
愛犬をバイクに乗せた際は、休憩と水分補給を小まめに行いましょう。
バイクツーリングは、犬にとって未知の体験です。そのため、エネルギーもかなり消耗します。
特に夏場は熱中症やパニックのリスクが高まります。
暑さに弱く、体温調整が苦手な犬にとって、ツーリング中にゲージやリュックでじっとしているのは、かなりのストレスになるのです。
休憩は少なくても1時間に1度は取りましょう。
その都度、水を飲ませてあげます。
夏場は地面やエンジンの暑さにも注意し、可能であれば保冷剤などをタオルにくるんでリュックやゲージに入れてあげると良いでしょう。
自分ひとりであれば、長く乗り続けたり、休憩せずに目的地へ辿り着くことも可能です。
ですが、犬はそうはいきません。不安定で振動や騒音のあるバイクに乗るだけで、大きなストレスになります。
その点を理解した上で、休憩をこまめにとってあげましょう。
体調不良のサインは絶対に見逃してはいけません。
出先ではすぐに動物病院にかかれない場合もあるため、いち早く異変に気付き、迅速に対処しないと重篤な状態になる恐れがあります。
次のような場合は、すぐにツーリングを中止し、病院へ行きましょう。
心配し過ぎてはツーリングを楽しめませんが、このようなリスクがあることを理解したうえでツーリングすべきです。
犬は体調不良を訴えることができません。
体調管理は飼い主の責任になります。
愛犬に安心して楽しんでもらうためにも、通り道に動物病院がないか調べたり、体調不良時の対策グッズなどを準備しておきましょう。
原付バイクに愛犬を乗せる場合は、特に注意が必要です。
原付バイクは小回りがききますが、車体も小さく、パワー不足のため不安定になりやすいです。
体重があり、落ち着きのないワンちゃんが乗ると、走行中に転倒するなどのリスクが高まります。
原付で乗せる場合は、次の点に注意しましょう。
原付は小さく小回りが利くので使い勝手が良いですが、その分、不安定なバイクです。

慣れているし、そんなに遠くに行かないから大丈夫
と慢心すると、大変な事故を起こしてしまう可能性があります。
慎重すぎるくらいに運転を行っていきましょう。

ここまで、愛犬とバイクに乗る方法について解説してきました。
まとめると次のようになります。
バイクと愛犬のサイズごとのオススメ商品は、ここを参考にしてね
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | |
| スクーター | サイドカーなど の特殊装備 |
||
| 中型・大型バイク | |||
| 原付 |
バイク好きの方にとって、愛犬とのタンデムツーリングは楽しく、嬉しい瞬間でしょう。
一緒に乗れるのであれば、ぜひ愛犬とお出かけしたいですよね。
ただし、そのためには十分な知識と準備が必要です。
適当に乗せてしまうと、法律違反になってしまうばかりか、人や愛犬の命に関わるような事態になってしまいかねません。それだけは絶対に避けたいですよね。
そうならないためにも、法律を正しく理解し、安全なグッズを揃え、十分な練習を積んでからツーリングに出かけましょう。
1つずつ着実に進めば、愛犬とのバイクライフはすぐそこです。スモールステップで頑張っていきましょう。
モトスポットでは、他にもバイクやツーリングに役立つ様々な情報やサービスが無料で利用できます!
バイクをもっと楽しくする情報
> バイクに役立つ情報を見る
全国のライダーおすすめツーリングスポット検索
> ツーリングスポット探す
自動ツーリングルート作成ツール
> 自動ツーリング作成ツールを使う
誰でもツーリングブログ投稿
> みんなのツーリングブログを見る




![PXLAATY バイク用 シフトブレーキ 挟んでロック 簡単操作 グリップ ブレーキ アクセルロック 盗難防止 セキュリティ 強化 バイク用品 スペアキー付属 ハンドル (ブラック) [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41TgPKE64IL._SL160_.jpg)



バイクの燃費向上・改善に効果的な走り方やメンテナンス方法を徹底解説!
バイクの燃費が気になる方は必見!この記事では、燃費を良くする走り方やメンテナンス方法を紹介しています。実は、車体そのものや荷物を軽くすることで、燃費の向上が可能です。この記事を読めば、燃費を改善する具体的な方法がわかります。

バイク買取歴8年の業者に聞いたバイクを高く売る方法
バイクを高く売るコツや方法について、実際にバイク買取業者として8年勤務している担当者に話を聞いてきました!高く買い取ってもらえるバイクの特徴や業者がどのくらい利益を上乗せしているかなど、バイクを売ろうとしている人は必見の内容になっています。

バイクエンジンの種類を徹底解説!気筒数や形式、冷却方法でフィーリングは違う
「バイクの性能はエンジンで決まる」と言っても過言ではありません。バイクにとってエンジンは、それだけ重要なパーツなんです。エンジンの種類と特徴を知れば、あなたもワンランク上のバイク選びができるようになります!
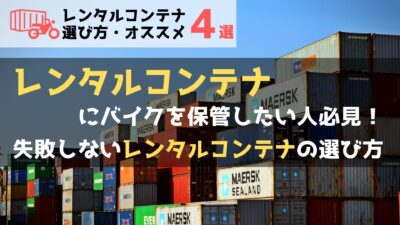
【保存版】バイク保管用のレンタルコンテナの選び方とオススメは?
バイク置き場としてレンタルコンテナを検討している方へ。バイクコンテナを選ぶ時に見るべき4つのポイントとオススメのレンタルコンテナ会社を徹底解説。これさえ読めば自分に最適なレンタルコンテナを見つけることができます。
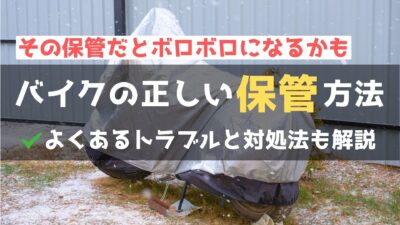
バイクの保管方法を徹底解説|注意点やよくあるトラブルも紹介!
バイクの保管についてお悩みの方は必見!この記事では、バイクの保管方法を詳しく解説します。実は適切に保管しなければ、バイクの状態を悪化させる恐れがあります。記事を参考にすれば、バイクを状態良く長持ちさせることが可能です。
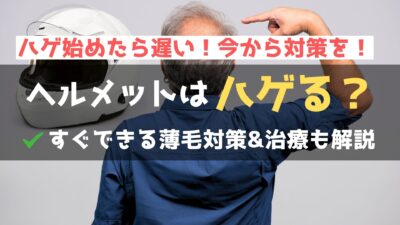
ヘルメットが禿げる原因って本当?!ライダーが知っておきたい薄毛対策!
バイク乗りの必須アイテム「ヘルメット」。道路交通法で着用が定められており、万が一の際に頭部を守るために被るものです。しかし、「ヘルメットが原因で禿げたらどうしよう」と心配しているライダーもいるのではないでしょうか。ライダーヘルメットが禿げる原因になるって本当かな・・・ライダーバイクには乗りたいけど抜け毛が増えたら困る!ライダーツーリング後に髪のボリュームが減った気がするけど、蒸れは禿げる原因になる?今回はこのような疑問、お悩みにお答えしていきます。薄毛が気になるライダーの方はぜひ最後まで

バイクの振動でスマホは壊れる!スマホホルダーは振動対策済みがオススメ
バイク用のスマホホルダーを探している人必見!iPhoneのカメラはバイクの振動で壊れます。スマホを壊す前に、振動対策がされたスマホホルダーを使うようにしましょう。カメラを壊さないための4つの方法とオススメのスマホホルダーを紹介します。

【エンジン選び】2サイクルと4サイクルの違いをわかりやすく解説!
バイクのエンジン選びに迷っている方は必見!この記事では、2サイクルエンジンと4サイクルエンジンの特徴やメリット、選び方を解説しています。実は、4サイクルエンジンは燃費が良く経済的で扱いやすいため、初心者の方にはおすすめです。記事を読めば、最適なエンジン選びのヒントが得られます。

【モトブログの始め方】機材選びや撮影テクニック、編集方法を徹底解説
モトブログの始め方を知りたい人必見!この記事では、モトブログの始め方から成功のコツまでを解説します。実は、モトブログを始めるには機材をそろえる必要があります。記事を読めば、モトブログを成功させるためのコツを知ることが可能です。

バイクのタイヤのひび割れは危険?!許容範囲や劣化を防ぐ方法も解説!
タイヤのひび割れは軽程度なら問題なく走行可能ですが、重度になってくるとバーストの危険もあるため交換が必要です。どの程度なら大丈夫なのか、タイヤのひび割れを防ぐ方法などまとめました。快適安全にバイクに乗るためにもしっかりとチェックしておきましょう。
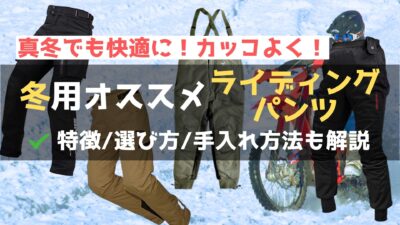
【4タイプ12選】オススメ冬用ライディングパンツで寒さ知らずのバイクツーリング
真冬でも暖かく快適にバイクに乗りたい人必見!!寒さは足や腰回りから来ます。足の寒さ対策をしっかりとすることで、体全体の寒さを防ぎ快適なバイクツーリングを楽しむことができます。この記事では、4つのタイプ別に真冬でも使えるライディングパンツを12選紹介します!

中古バイク選びで絶対見るべき12のポイント!初心者でも失敗しない選び方
初めて中古バイクを購入する人にとって、バイクの状態を見分けることは難しいですよね。でも実は、知識ゼロの初心者でも「12のポイント」に注目するだけで、中古バイクの良し悪しを簡単に判断することができるんです!正しいポイントを押させて失敗しないバイク選びができるようになりましょう。
コメント
コメント
名前
ログインすると、コメントの削除やアイコンの設定ができます。